![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 災害救援・地域安全活動
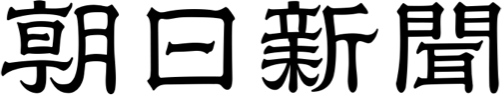
なぜ被災地で重機に乗るのか 能登の復興支える技術系ボランティア
2025.04.09

全国で頻発する災害で、発災から間もないうちに、重機や資機材とともに駆けつけるボランティアたちがいる。発災直後に、土砂で埋もれた道路を通したり、倒壊家屋から車両や貴重品を取り出したりするだけでなく、泥につかった家屋の再生、屋根の修繕、倒れ込んだ木々の伐採など、中長期的に住民の困りごとに寄り添う。声を上げにくい人の声に耳を傾け、生業(なりわい)や地域のよりどころの復旧といった、公的支援が行き届かない場所に目を向ける。
災害支援ネットワーク「DRT JAPAN」は、そうした全国の技術系ボランティアたちが、互いに連携するハブ(中心)のひとつだ。
昨年1月の能登半島地震直後から、7月に起きた山形県北部豪雨の復旧支援を挟み、ほぼ毎日、活動を続けてきた。
手弁当で災害支援を続けることは容易ではない。それでも支援に入るのは――。DRTに集う人たちの横顔を追った。
■「また来よう。そんな気持ちがずっと続いてる」杉田直樹さん/土建業(広島県)
「災害では気をつかうポイントがすごく多いんよ」。土建業を営み、治山ダム建設などの大型工事も請け負う杉田直樹さんに、普段の仕事と被災地での活動の違いを尋ねると、そう返ってきた。
通常の工事現場では、前もって決められた工程をプロどうしが進めていくが、被災地では、経験が浅い人や一般のボランティアらもいる中で可能な作業工程を、その都度判断していく。操縦する重機のすぐそばを通ろうとする人もいる。杉田さんは、危険予知をしながら、誰がどこで何をしているのか、常に目を光らせる。家屋から土砂を取り出す際には、廊下や壁を傷つけないよう、細心の注意を払う。
東日本大震災以降、見過ごされがちな小さな被災集落にも足を運んできた。地元の広島から被災地へ重機を積んで入り、仕事で戻るときに「ほかの人が使えるように」と置いて帰ることもある。
「なんで通うのか、って? まだやれることがあるのに、仕事があるけぇ帰らにゃいけん。じゃけぇまた来よう。そんな気持ちがずっと続いてる。休みの保養で来てるみたいなもんよ」と杉田さんはこともなげに笑う。「関心があっても、来られる状態じゃない人もおる。だから来るのがすべてじゃない。ただ、多くの人が寄り添う気持ちを持ってくれていればいいな」
■「救助の先に、助けなきゃいけない命がいっぱいあった」我妻清和さん/消防士(山形県)
昨年7月、山形県の消防士、我妻清和さんは、3連休をとって能登半島地震の被災地支援に向かう途中で、地元の豪雨災害を知った。急きょ引き返し、重機とダンプカーを地元の業者に借りて、土砂でふさがった道路を開きながら、被災状況や、どんな支援が必要なのかを調べてまわった。
「できることをやろう。背伸びせず、誰かのためになることをひとつでもしよう。そう言って仲間と手分けしました」。能登半島地震後、本業は消防士や大工といった地元の仲間たちと、地元が被災したら率先して動こう、と災害支援チームを立ち上げていた。
水路を埋める側溝の泥を出したり、お墓を埋める土砂を撤去したり、地域の災害ボランティアセンターと連携して住民の要望に応えようと努めた。能登半島で支援を続ける仲間も駆けつけてくれた。
どの被害対応を優先するのか、どこまで復旧に携わるのか。限られた人員、重機、資機材をどう配置するのか。2年半前に隣県の水害でボランティアに参加して以来、経験を重ねてきたが、中心となって支援の方向性を組み立てるのは初めて。すべてが手探りだった。「支援スキルはまだまだだけど、まずは動かなきゃ、と。もっと技術面も制度面も勉強して『うちもあんなチームをつくりたい』って思ってもらえるような姿を見せていきたい」と我妻さんは言う。
「消防の仕事は救助まで。だけどその先に、助けなきゃいけない命がいっぱいあった」。被災後の生活の変化が心身に与える影響を、災害支援活動の中で知った。勤務明けや休暇のほとんどを使って、被災地に通う理由だ。
全国各地に技術系ボランティアチームがあれば、それぞれの地元で災害が起きたときに、連携しあい、素早い救援を実現できる。そうして皆で命を守っていけたら。そんな未来を描いている。(川村直子)
災害支援ネットワーク「DRT JAPAN」は、そうした全国の技術系ボランティアたちが、互いに連携するハブ(中心)のひとつだ。
昨年1月の能登半島地震直後から、7月に起きた山形県北部豪雨の復旧支援を挟み、ほぼ毎日、活動を続けてきた。
手弁当で災害支援を続けることは容易ではない。それでも支援に入るのは――。DRTに集う人たちの横顔を追った。
■「また来よう。そんな気持ちがずっと続いてる」杉田直樹さん/土建業(広島県)
「災害では気をつかうポイントがすごく多いんよ」。土建業を営み、治山ダム建設などの大型工事も請け負う杉田直樹さんに、普段の仕事と被災地での活動の違いを尋ねると、そう返ってきた。
通常の工事現場では、前もって決められた工程をプロどうしが進めていくが、被災地では、経験が浅い人や一般のボランティアらもいる中で可能な作業工程を、その都度判断していく。操縦する重機のすぐそばを通ろうとする人もいる。杉田さんは、危険予知をしながら、誰がどこで何をしているのか、常に目を光らせる。家屋から土砂を取り出す際には、廊下や壁を傷つけないよう、細心の注意を払う。
東日本大震災以降、見過ごされがちな小さな被災集落にも足を運んできた。地元の広島から被災地へ重機を積んで入り、仕事で戻るときに「ほかの人が使えるように」と置いて帰ることもある。
「なんで通うのか、って? まだやれることがあるのに、仕事があるけぇ帰らにゃいけん。じゃけぇまた来よう。そんな気持ちがずっと続いてる。休みの保養で来てるみたいなもんよ」と杉田さんはこともなげに笑う。「関心があっても、来られる状態じゃない人もおる。だから来るのがすべてじゃない。ただ、多くの人が寄り添う気持ちを持ってくれていればいいな」
■「救助の先に、助けなきゃいけない命がいっぱいあった」我妻清和さん/消防士(山形県)
昨年7月、山形県の消防士、我妻清和さんは、3連休をとって能登半島地震の被災地支援に向かう途中で、地元の豪雨災害を知った。急きょ引き返し、重機とダンプカーを地元の業者に借りて、土砂でふさがった道路を開きながら、被災状況や、どんな支援が必要なのかを調べてまわった。
「できることをやろう。背伸びせず、誰かのためになることをひとつでもしよう。そう言って仲間と手分けしました」。能登半島地震後、本業は消防士や大工といった地元の仲間たちと、地元が被災したら率先して動こう、と災害支援チームを立ち上げていた。
水路を埋める側溝の泥を出したり、お墓を埋める土砂を撤去したり、地域の災害ボランティアセンターと連携して住民の要望に応えようと努めた。能登半島で支援を続ける仲間も駆けつけてくれた。
どの被害対応を優先するのか、どこまで復旧に携わるのか。限られた人員、重機、資機材をどう配置するのか。2年半前に隣県の水害でボランティアに参加して以来、経験を重ねてきたが、中心となって支援の方向性を組み立てるのは初めて。すべてが手探りだった。「支援スキルはまだまだだけど、まずは動かなきゃ、と。もっと技術面も制度面も勉強して『うちもあんなチームをつくりたい』って思ってもらえるような姿を見せていきたい」と我妻さんは言う。
「消防の仕事は救助まで。だけどその先に、助けなきゃいけない命がいっぱいあった」。被災後の生活の変化が心身に与える影響を、災害支援活動の中で知った。勤務明けや休暇のほとんどを使って、被災地に通う理由だ。
全国各地に技術系ボランティアチームがあれば、それぞれの地元で災害が起きたときに、連携しあい、素早い救援を実現できる。そうして皆で命を守っていけたら。そんな未来を描いている。(川村直子)
