![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 災害救援・地域安全活動
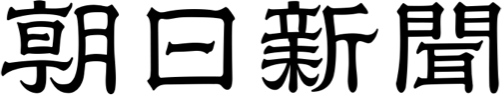
災害復旧に集う「技術系ボランティア」とは? 町の景色を変える意味
2025.04.09

全国で頻発する災害で、発災から間もないうちに、重機や資機材とともに駆けつけるボランティアたちがいる。発災直後に、土砂で埋もれた道路を通したり、倒壊家屋から車両や貴重品を取り出したりするだけでなく、泥につかった家屋の再生、屋根の修繕、倒れ込んだ木々の伐採など、中長期的に住民の困りごとに寄り添う。声を上げにくい人の声に耳を傾け、生業(なりわい)や地域のよりどころの復旧といった、公的支援が行き届かない場所に目を向ける。
災害支援ネットワーク「DRT JAPAN」は、そうした全国の技術系ボランティアたちが、互いに連携するハブ(中心)のひとつだ。
昨年1月の能登半島地震直後から、7月に起きた山形県北部豪雨の復旧支援を挟み、ほぼ毎日、活動を続けてきた。
手弁当で災害支援を続けることは容易ではない。それでも支援に入るのは――。DRTに集う人たちの横顔を追った。
■「なすすべがなかった東日本大震災」 稲富慎二郎さん/消防士(宮城県)
2011年、消防士になって5年目に起きた、東日本大震災。宮城県の消防士、稲富慎二郎さんは、家族を内陸部に残し、泊まり込みで沿岸の捜索活動にあたった。津波で流された倒壊家屋や車の中を、ひとつひとつ覗(のぞ)いては退き、がれきの上を歩く日々。「命を救うため消防士になったのに、なすすべがなかった」
19年には、県南部を台風19号が襲った。東日本大震災をきっかけに全国の消防に重機が配備され、その操縦訓練を積んだ稲富さんは、オペレーターとして現場へ向かった。
だが、重機の使用許可は下りず、活用できる場面で動けなかった。
もどかしさを抱えていたとき、災害支援で重機を扱う「技術系」と呼ばれるボランティアたちと出会った。被災家屋から土砂や車両を出したり、がれきでふさがれた道路を通したり。住民の財産を傷つけないよう細心の注意を払い、不安定な足場でも素早く作業を進めていく姿に圧倒された。
「そばで学びながら、自分も役に立ちたい」と休暇を使って活動を共にするようになった。その経験を話すと、職場の仲間たちも後に続き始めた。
昨年5月、そうした仲間たちと、災害支援団体「Five_up_SENDAI」を立ち上げた。消防の仕事の合間を縫って、能登半島地震や山形県の豪雨災害の被災地に通う傍ら、地元では土石流などの二次災害を防ぐため、荒廃した里山林の整備に力を入れる。木の状態を見て、腐っていないかなど危険性を判断し、安全な木の倒し方やチェーンソーの技術も訓練している。
2月下旬に岩手県大船渡市で起きた山林火災では、小隊を率いて消火にあたった。根元が焼け細ったり傾いたりしている危険な木々に囲まれた急しゅんな斜面で、安全を確保しながら活動する上で、災害支援の活動が役立ったという。
「技術を身につけること、それをいかすことで、救助や救援の可能性は広がる。消防の現場でも活用されるよう、自分たちが何ができるのかを、行動で示していきたい」
■「技術は対話のツール」 黒澤司さん/団体職員(神奈川県)
「最初は『自分なんかが行っていいのかな』って躊躇(ちゅうちょ)したよ」。DRTを率いる黒澤司さんは、初めて重機講習を受けた20年前をそう振り返る。
ボランティアといえば、スコップひとつで泥だしをするのが主流だった頃。当時、そうした講習を受けるのは、ほとんどが建設業に携わる人たちだった。
阪神大震災以来、国内外で災害支援を重ねる中で、人力の何十倍ものスピードとパワーで復旧作業を進められる小型重機を被災地で活用できたら、と考えるようになった。
壊れた家屋や道路を応急復旧し、目の前の景色を変えることは、住民のふさぐ気持ちを少しでも変えていくことにつながる。被災した人たちの負担を和らげ、生活再建の選択肢を増やすために、スピード感をもって動く。だが決して決断を急かしたり、自分たちの考えを押しつけたりはしない。
そうした思いを共にする仲間たちとネットワークを組織して、自治体や災害ボランティアセンターとの連携を丁寧に進めた。いまや、重機操縦を含む技術系ボランティアは、全国で頻発する災害の復旧・復興に必要不可欠な存在だ。
その先頭に立つ黒澤さんは、災害支援のための重機やチェーンソーの講習会を定期的に開き、次世代の育成にも力を注いでいる。
「技術はもちろん、『聞く力』の大切さを、そばで学んでいます」と前出の稲富慎二郎さんは言う。同じ災害であっても、被災状況や家族構成、仕事などの事情は住民それぞれに違う。個々の困りごとを聞きとることで初めて、住民目線の支援ができる。
「技術はあくまでもツール」と黒澤さん。つねに被災地をまわり、公的支援制度から取り残されている人に心を寄せる。住民の声に耳を傾け、何げない会話の中から被災後の生活をイメージして、必要な支えを仲間たちと届けていく。(川村直子)
災害支援ネットワーク「DRT JAPAN」は、そうした全国の技術系ボランティアたちが、互いに連携するハブ(中心)のひとつだ。
昨年1月の能登半島地震直後から、7月に起きた山形県北部豪雨の復旧支援を挟み、ほぼ毎日、活動を続けてきた。
手弁当で災害支援を続けることは容易ではない。それでも支援に入るのは――。DRTに集う人たちの横顔を追った。
■「なすすべがなかった東日本大震災」 稲富慎二郎さん/消防士(宮城県)
2011年、消防士になって5年目に起きた、東日本大震災。宮城県の消防士、稲富慎二郎さんは、家族を内陸部に残し、泊まり込みで沿岸の捜索活動にあたった。津波で流された倒壊家屋や車の中を、ひとつひとつ覗(のぞ)いては退き、がれきの上を歩く日々。「命を救うため消防士になったのに、なすすべがなかった」
19年には、県南部を台風19号が襲った。東日本大震災をきっかけに全国の消防に重機が配備され、その操縦訓練を積んだ稲富さんは、オペレーターとして現場へ向かった。
だが、重機の使用許可は下りず、活用できる場面で動けなかった。
もどかしさを抱えていたとき、災害支援で重機を扱う「技術系」と呼ばれるボランティアたちと出会った。被災家屋から土砂や車両を出したり、がれきでふさがれた道路を通したり。住民の財産を傷つけないよう細心の注意を払い、不安定な足場でも素早く作業を進めていく姿に圧倒された。
「そばで学びながら、自分も役に立ちたい」と休暇を使って活動を共にするようになった。その経験を話すと、職場の仲間たちも後に続き始めた。
昨年5月、そうした仲間たちと、災害支援団体「Five_up_SENDAI」を立ち上げた。消防の仕事の合間を縫って、能登半島地震や山形県の豪雨災害の被災地に通う傍ら、地元では土石流などの二次災害を防ぐため、荒廃した里山林の整備に力を入れる。木の状態を見て、腐っていないかなど危険性を判断し、安全な木の倒し方やチェーンソーの技術も訓練している。
2月下旬に岩手県大船渡市で起きた山林火災では、小隊を率いて消火にあたった。根元が焼け細ったり傾いたりしている危険な木々に囲まれた急しゅんな斜面で、安全を確保しながら活動する上で、災害支援の活動が役立ったという。
「技術を身につけること、それをいかすことで、救助や救援の可能性は広がる。消防の現場でも活用されるよう、自分たちが何ができるのかを、行動で示していきたい」
■「技術は対話のツール」 黒澤司さん/団体職員(神奈川県)
「最初は『自分なんかが行っていいのかな』って躊躇(ちゅうちょ)したよ」。DRTを率いる黒澤司さんは、初めて重機講習を受けた20年前をそう振り返る。
ボランティアといえば、スコップひとつで泥だしをするのが主流だった頃。当時、そうした講習を受けるのは、ほとんどが建設業に携わる人たちだった。
阪神大震災以来、国内外で災害支援を重ねる中で、人力の何十倍ものスピードとパワーで復旧作業を進められる小型重機を被災地で活用できたら、と考えるようになった。
壊れた家屋や道路を応急復旧し、目の前の景色を変えることは、住民のふさぐ気持ちを少しでも変えていくことにつながる。被災した人たちの負担を和らげ、生活再建の選択肢を増やすために、スピード感をもって動く。だが決して決断を急かしたり、自分たちの考えを押しつけたりはしない。
そうした思いを共にする仲間たちとネットワークを組織して、自治体や災害ボランティアセンターとの連携を丁寧に進めた。いまや、重機操縦を含む技術系ボランティアは、全国で頻発する災害の復旧・復興に必要不可欠な存在だ。
その先頭に立つ黒澤さんは、災害支援のための重機やチェーンソーの講習会を定期的に開き、次世代の育成にも力を注いでいる。
「技術はもちろん、『聞く力』の大切さを、そばで学んでいます」と前出の稲富慎二郎さんは言う。同じ災害であっても、被災状況や家族構成、仕事などの事情は住民それぞれに違う。個々の困りごとを聞きとることで初めて、住民目線の支援ができる。
「技術はあくまでもツール」と黒澤さん。つねに被災地をまわり、公的支援制度から取り残されている人に心を寄せる。住民の声に耳を傾け、何げない会話の中から被災後の生活をイメージして、必要な支えを仲間たちと届けていく。(川村直子)
