![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 医療・福祉・人権
- 子ども・教育
- 多文化共生・国際協力
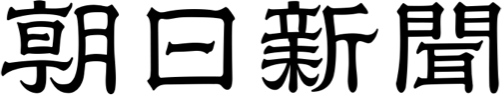
滋賀県内に初の夜間中学 19歳、夢に向かって「また学べる」
2025.04.03

滋賀県内初の夜間中学として湖南市立「甲西中学校夜間学級」が今月開校する。初年度の入学者は10~60代の21人。外国にルーツのある入学者が12人、学び直しの入学者が9人という。戦後の混乱期に生まれた夜間中学が、なぜ求められているのか。(林利香)
「また学校で学ぶことができてうれしい」
入江夢さん(19)=湖南市=は、入学を心待ちにしている。夜間中学では2年生からスタートする。「じっくり勉強したい。夜間中学は将来につながるとっても大事な場所」
日系3世のブラジル人。日本で生まれ育ち、小学1年から中学1年まで公立学校に通い、中学2年からは東近江市のブラジル人学校で学んだ。だが高等部2年の時、中学の恩師がいた湖南市教育委員会に「日本の高校に通いたい」と相談に行った。日本に住み続け、日本の文化や生活を学びたいとの思いが募ったからだ。
市の少年センターに通い、高校入学のための中学校卒業程度認定試験を受けた。1年目は英語と社会の2教科に合格したが、残り3教科でも合格しなければならない。そんな時、湖南市に夜間中学の開校が決まった。「びっくりした。私の人生の中でこんなチャンスが巡ってくるなんて」と声を弾ませる。
今は、湖南市立の小学校の母語支援員として、ブラジルの子どもたちの授業や保護者への連絡のサポートをしている。夜間中学を卒業した後は日本の高校、大学への進学をめざす。「心理学の先生になって、不安な気持ちを抱えた子どもたちに寄り添いたい」という。開校日は、夢に向かう新たな門出の日だ。
◇
文部科学省によると、2024年10月時点の公立夜間中学は全国で32の都道府県と政令指定市に53校ある。22年の前回調査より13校増え、夜間中学に通う生徒は1969人で前回の約1・3倍に増加した。国籍を問わず、39歳以下の若年層の生徒が増えているという。
川崎市で夜間学級を併設した中学校長を6年間務めた安部賢一・神奈川大学特任教授に公立夜間中学の役割について聞いた。
――今なぜ夜間中学が増えているのですか?
戦後、中学に通えない子どもたちのために教員が自発的に始めたのが夜間中学の始まりです。高度経済成長が進むと生徒は減少して夜間中学も急激に減り、1966年に国は「夜間中学早期廃止勧告」を出しました。
ただ、その後も在日コリアンの方や中国からの帰国者、2000年代には外国人労働者の増加に伴い、外国にルーツを持つ学齢超過者の受け皿となってきました。
一方で、10年代後半には不登校が急増し社会問題となりましたが、不登校などで学校に行けないまま中学を卒業した「形式卒業者」の多くは、一度卒業したという理由で夜間中学に入れませんでした。
転換点が、16年に成立した「教育機会確保法」です。国は初めて夜間中学を法的に位置づけ、これをきっかけに形式卒業者や日本語ができない外国人など、基礎教育を必要とする全ての学齢期を過ぎた人に夜間中学への門戸が開かれました。国は、全都道府県と指定都市に、1校以上の設置をめざしています。
――滋賀に夜間中学のニーズはあるのでしょうか?
県内には、学びを支援する市民団体がほとんどなく、ニーズが少ないとみなして、公立の設置に通常消極的になります。その中で、設置を決めた湖南市と滋賀県を評価しています。
全国の不登校の小中学生は35万人に迫ります。不登校は中学を卒業すると「不登校」の統計から外れます。国は、その後の追跡調査を行っていないため形式卒業者の実態すら把握されていません。私が文部科学省と県の不登校調査を元に推計したところ、34年には県内の15歳から29歳の若者のうち8千人が中学校の形式卒業者になると見込まれます。基礎教育を受けずに卒業する人が確実に増えているのです。
――湖南市にできる夜間中学の特徴は?
全国で夜間のみの「単独型」夜間中学の新設が進む中、既存の市立中学に「併設」されます。入学式や体育祭など合同の行事を通して、昼間の生徒も夜間中学の存在に触れられる。それによって、学びは学齢期を過ぎても終わりではない、「セカンド、サードチャンスが社会にはあるんだ」と、子どもたちに気付きを与えてくれるでしょう。
また、協定書や覚書を交わさずに県内他市町からも広く生徒を受け入れ、定員や在籍年数に制限を設けないことも大きな特徴です。
ただ、公立夜間中学は万能ではありません。仕事や家庭の都合で平日夜に毎日通えない人もいるからです。
そうした人たちを土日に支援する市民のボランティア組織が全国にあります。それが「自主夜間中学」です。学びたい人が1人いて教える人が1人いれば「自主夜間中学」になります。他の自治体では、自主夜間中学の学びをきっかけに公立夜間中学に入学する人もいます。「学びたい」「学び直したい」と思う全ての県民により裾野の広い学びの場が行き渡っていくことを願っています。
◇
湖南市教育長だった時期に夜間中学設置に尽力した松浦加代子市長に聞いた。
――なぜ、夜間中学の設置を進めたのですか?
市健康福祉部発達支援室の室長を4年間務めていました。そこでは、「学校で仲間と学び合う喜びを十分感じられなかった」や「中学校の卒業式に出られなかった」といった学校でつまずいた経験を持ついわゆる「形式卒業者」の青年をたくさん担当しました。私は元々教員なので、学校で仲間と一緒に学ぶ喜びや自尊感情を育んでほしい、と考えました。
また、湖南市は外国人人口の割合が7・42%と県内で最も高い。教頭をしていた小学校は約25%が外国にルーツのある子どもたちでした。働くために小中学校の卒業証書がほしいと相談に来られる保護者もいました。夜間中学は湖南市のニーズに一致すると思い、約3年かけて、先進地に視察に行くなど、準備を進めてきました。
――夜間中学に期待することは?
甲西中学に通う昼間の生徒や教職員にとって、夜間に通う生徒の「自ら学ぶ姿勢」を見ることは良い影響になる。「学び」とは知識を得ることだけではなく、「主体的に学んでいる人の姿をみて学ぶこと」だと思います。そんな仲間の姿を見られるのは学校です。
私が出会ってきた形式卒業者はみんな世に出てくる力を持った子たちです。相談できる大人と出会っておくか、誰と出会うか、だと思うんです。そんな出会いの場としても夜間中学の役割があると思います。夜間中学の生徒さんは世代も国籍も違います。ただ共通するのは「学びたい」「学び直したい」という思いです。県全体の「学ぶ」機運を高められる基点に夜間中学がなっていければいいな、と思っています。
「また学校で学ぶことができてうれしい」
入江夢さん(19)=湖南市=は、入学を心待ちにしている。夜間中学では2年生からスタートする。「じっくり勉強したい。夜間中学は将来につながるとっても大事な場所」
日系3世のブラジル人。日本で生まれ育ち、小学1年から中学1年まで公立学校に通い、中学2年からは東近江市のブラジル人学校で学んだ。だが高等部2年の時、中学の恩師がいた湖南市教育委員会に「日本の高校に通いたい」と相談に行った。日本に住み続け、日本の文化や生活を学びたいとの思いが募ったからだ。
市の少年センターに通い、高校入学のための中学校卒業程度認定試験を受けた。1年目は英語と社会の2教科に合格したが、残り3教科でも合格しなければならない。そんな時、湖南市に夜間中学の開校が決まった。「びっくりした。私の人生の中でこんなチャンスが巡ってくるなんて」と声を弾ませる。
今は、湖南市立の小学校の母語支援員として、ブラジルの子どもたちの授業や保護者への連絡のサポートをしている。夜間中学を卒業した後は日本の高校、大学への進学をめざす。「心理学の先生になって、不安な気持ちを抱えた子どもたちに寄り添いたい」という。開校日は、夢に向かう新たな門出の日だ。
◇
文部科学省によると、2024年10月時点の公立夜間中学は全国で32の都道府県と政令指定市に53校ある。22年の前回調査より13校増え、夜間中学に通う生徒は1969人で前回の約1・3倍に増加した。国籍を問わず、39歳以下の若年層の生徒が増えているという。
川崎市で夜間学級を併設した中学校長を6年間務めた安部賢一・神奈川大学特任教授に公立夜間中学の役割について聞いた。
――今なぜ夜間中学が増えているのですか?
戦後、中学に通えない子どもたちのために教員が自発的に始めたのが夜間中学の始まりです。高度経済成長が進むと生徒は減少して夜間中学も急激に減り、1966年に国は「夜間中学早期廃止勧告」を出しました。
ただ、その後も在日コリアンの方や中国からの帰国者、2000年代には外国人労働者の増加に伴い、外国にルーツを持つ学齢超過者の受け皿となってきました。
一方で、10年代後半には不登校が急増し社会問題となりましたが、不登校などで学校に行けないまま中学を卒業した「形式卒業者」の多くは、一度卒業したという理由で夜間中学に入れませんでした。
転換点が、16年に成立した「教育機会確保法」です。国は初めて夜間中学を法的に位置づけ、これをきっかけに形式卒業者や日本語ができない外国人など、基礎教育を必要とする全ての学齢期を過ぎた人に夜間中学への門戸が開かれました。国は、全都道府県と指定都市に、1校以上の設置をめざしています。
――滋賀に夜間中学のニーズはあるのでしょうか?
県内には、学びを支援する市民団体がほとんどなく、ニーズが少ないとみなして、公立の設置に通常消極的になります。その中で、設置を決めた湖南市と滋賀県を評価しています。
全国の不登校の小中学生は35万人に迫ります。不登校は中学を卒業すると「不登校」の統計から外れます。国は、その後の追跡調査を行っていないため形式卒業者の実態すら把握されていません。私が文部科学省と県の不登校調査を元に推計したところ、34年には県内の15歳から29歳の若者のうち8千人が中学校の形式卒業者になると見込まれます。基礎教育を受けずに卒業する人が確実に増えているのです。
――湖南市にできる夜間中学の特徴は?
全国で夜間のみの「単独型」夜間中学の新設が進む中、既存の市立中学に「併設」されます。入学式や体育祭など合同の行事を通して、昼間の生徒も夜間中学の存在に触れられる。それによって、学びは学齢期を過ぎても終わりではない、「セカンド、サードチャンスが社会にはあるんだ」と、子どもたちに気付きを与えてくれるでしょう。
また、協定書や覚書を交わさずに県内他市町からも広く生徒を受け入れ、定員や在籍年数に制限を設けないことも大きな特徴です。
ただ、公立夜間中学は万能ではありません。仕事や家庭の都合で平日夜に毎日通えない人もいるからです。
そうした人たちを土日に支援する市民のボランティア組織が全国にあります。それが「自主夜間中学」です。学びたい人が1人いて教える人が1人いれば「自主夜間中学」になります。他の自治体では、自主夜間中学の学びをきっかけに公立夜間中学に入学する人もいます。「学びたい」「学び直したい」と思う全ての県民により裾野の広い学びの場が行き渡っていくことを願っています。
◇
湖南市教育長だった時期に夜間中学設置に尽力した松浦加代子市長に聞いた。
――なぜ、夜間中学の設置を進めたのですか?
市健康福祉部発達支援室の室長を4年間務めていました。そこでは、「学校で仲間と学び合う喜びを十分感じられなかった」や「中学校の卒業式に出られなかった」といった学校でつまずいた経験を持ついわゆる「形式卒業者」の青年をたくさん担当しました。私は元々教員なので、学校で仲間と一緒に学ぶ喜びや自尊感情を育んでほしい、と考えました。
また、湖南市は外国人人口の割合が7・42%と県内で最も高い。教頭をしていた小学校は約25%が外国にルーツのある子どもたちでした。働くために小中学校の卒業証書がほしいと相談に来られる保護者もいました。夜間中学は湖南市のニーズに一致すると思い、約3年かけて、先進地に視察に行くなど、準備を進めてきました。
――夜間中学に期待することは?
甲西中学に通う昼間の生徒や教職員にとって、夜間に通う生徒の「自ら学ぶ姿勢」を見ることは良い影響になる。「学び」とは知識を得ることだけではなく、「主体的に学んでいる人の姿をみて学ぶこと」だと思います。そんな仲間の姿を見られるのは学校です。
私が出会ってきた形式卒業者はみんな世に出てくる力を持った子たちです。相談できる大人と出会っておくか、誰と出会うか、だと思うんです。そんな出会いの場としても夜間中学の役割があると思います。夜間中学の生徒さんは世代も国籍も違います。ただ共通するのは「学びたい」「学び直したい」という思いです。県全体の「学ぶ」機運を高められる基点に夜間中学がなっていければいいな、と思っています。
